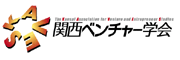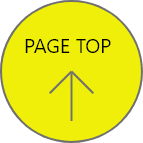カテゴリー別アーカイブ: 事務局からのお知らせ
2021年度第2回地域創造研究部会ご案内
この度,下記のとおり研究部会を開催することになりましたので,ご案内します。多くの方のご参加をお待ちしています。
1.日時:令和3年6月19 日(土)午前10時00分~11時30分
2.場所:ZOOMにて(詳細は,参加申し込みの方に別途ご連絡します)
3.テーマ:「エフェクチュエーションの理論と実践-熟達した起業家の意思決定-」
4.講師:京都大学経営管理大学院
特定助教 高瀬 進 氏
 <ご経歴>
<ご経歴>
・1994年神戸大学工学部システム工学科卒。
・2013年神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了。博士(経営学)。
・山口大学技術経営研究科、京都大学工学研究科ロボティクス研究室を経て、現職。
<主要論文・著作>
・『大学発ベンチャー起業家の「熟達」研究 瀧和男のライフヒストリー』(中央経済社, 2017年)
・『エフェクチュエーション』(碩学舎, 2015年)[翻訳-共著]
・『大学発ベンチャーか、技術移転か』(日本ベンチャー学会誌, 2013)[共著]等
5.費用:会員―無料。
当研究部会への参加が初めての方(非会員)は無料。
上記以外の方は1,000円(学生は500円)となり,銀行振込にてお支払いをお願いします。
詳細は,申込み後に,ご連絡させていただきます。
6.定員:15名
7.問合せ・参加申込先
参加希望者は,氏名,会員・非会員の区分,所属,メールアドレスを明記の上,下記までお申し込みください。
お申し込みのあった方に,講演会開催の2日前までZOOM URLをお知らせする予定です。
関西ベンチャー学会地域創造研究部会 主査:文能照之,幹事:大野長八
E-mail : tbunno@bus.kindai.ac.jp
Tel :06-4307-3292、FAX:06-6729-2493
第1回 「AI+農業+経営」プロジェクト研究部会
・日時:2021年5月13日(木) 18:30~20:00
・ZOOM方式:https://us02web.zoom.us/j/86045820087?pwd=WmJsTjdCWWR5QXZuOUt2YVg5QTBTQT09
ミーティングID: 860 4582 0087
パスコード: 491589
・講題:植物工場と新たな日本の農業(仮題)
・講演者:森久エンジニアリング(株) 社長 森 一生氏
森久エンジニアリングでは、固定概念に挑戦し、新たな創造を行ってまいりました。例えば、露地栽培の農業と植物工場の農業はまったく正反対の方向で生産を行っています。露地栽培は、絶えず変化する自然環境に対して、季節と土地と種という条件をうまく組み合わせて何とか自然環境に適応させる環境適応技術と言い換えることができます。一方で、植物工場による野菜栽培は、野菜の持つ成長条件をうまく引き出すため環境を野菜の好む条件に調節し、最適成長を導き出す環境適合技術と言い換えることができます。つまり、野菜を環境に調和させる栽培が露地栽培であるのに対して、環境を野菜に調和させる栽培が植物工場であり、考え方が真逆になっているのです。従来の伝統的な農業生産に新たに加えられる新技術農業の創造は、わが国の農業生産の厚みを増し、今後の農業の将来性を大きく切り開いていくことになると信じています。 科学技術の進歩は、技術課題に素直な目で向き合うことが原点であると思います。固定概念の打破こそが当社の今後のビジネスを拡大発展させ得る大きな原動力になると信じて今後も挑戦してまいります。
2020年3月 ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ2020優秀賞を受賞
ご参加お申込み:定藤繁樹 sadato333@ybb.ne.jp
知的財産研究部会開催のお知らせ(5/24 15:30から)
日時 5月24日(月) 15:30から17:00
方法 WEB zoom
講演内容 大阪産業局のベンチャー支援策について
講師 大阪産業局 イノベーション推進部
部長 中村 奈依 様
従来大阪府および大阪市は、BOOMINGやOSAPなどベンチャー支援を
それぞれ実施されてこられ、実績も出されています。
今般公益法人大阪産業局が一手に大阪府と大阪市のベンチャー支援策を実施され
効率化を図られることとなりました。
このため、大阪産業局 イノベーション推進部 部長の
中村 奈依 様から大阪産業局のベンチャー支援策全般につきまして
Web(zoom)でご説明いただけることとなりました。
皆様ぜひご参加ください。
ご参加お申込み先:林茂樹 shigeki.hayashi@oit.ac.jp
第7回ビジネスモデルとベンチャー研究部会
第7回ビジネスモデルとベンチャー研究部会開催のご案内
日時:2021年5月8日(土)10:00~12:30
場所:オンライン(ZOOM)で行います。
参加申込:(参加費は無料)メールで下記をご記入の上、お申し込みください。5月7日~8日に、ご記入頂いたメールアドレス宛にZOOM会場に入場用のURL,ID/PWをお送りします。申し込みの表題は「第7回ビジネスモデルとベンチャー研究部会に参加」でお願いします。1.お名前:( ) 2.ご所属名:( ) 3.メールアドレス:( ) 4.電話番号:( ) 宛先(申込受付)konishikazu@gmail.com(主査:小西一彦)
——————————————————————————–
第1報告:「ネクストシリコンバレー、イスラエルのエコシステム」(10:00~11:00)
講師:三森八重子氏(関西ベンチャー学会会員、大阪大学・招聘教授)
<プロフィール> 文部科学省科学技術政策研究所, 独立行政法人理化学研究所, 国立大学法人東京工業大学, 国立大学法人筑波大学国際経営プロフェッショナル専攻(MBA-IB)准教授を経て, 2015年より国立大学法人大阪大学高等教育入試研究開発センター教授。2020年4月より大阪大学招聘教授。米ハーバード大学ケネディスクールより行政学修士(MPA)取得。東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻より 博士(工学)取得。専門は技術経営・技術管理(MOT)。PICMET, 米国科学振興協会(AAAS), IEEE, 研究イノベーション学会(評議員), 日本MOT学会(理事),日本経営システム学会(常任理事), 日本生産管理学会(代議員), 関西ベンチャー学会会員。日米研究インスティチュート(USJI)(協力員)。東洋大学国際学部グローバルイノベーション学科非常勤講師、筑波大学大学院医学医療系非常勤講師。
<講演内容の概要>イスラエルは日本の四国ほどの領土しかないが、イノベーションの先進国として注目を集めており、第2のシリコンバレーとも呼ばれる。イスラエルには278社のグローバルICT企業が327のR&D拠点を置いており、多額の資金が投入されている。2018年のイスラエルへの直接投資額は210億円と、5年前に比較して倍増した。また、とりわけロシアから多くの移民を受け容れてきたこともあり、人口は過去30年で倍増した。加えてイスラエル人は家族を大切にする習性があり、出生率が3.11と比較的高く維持されている。世界の先進諸国の経済は2000年以降伸び悩んでいるが、ハイテク産業の好況を背景にイスラエルの経済は日本や欧米諸国を上回る成長率を維持している。例えば2017年のイスラエルのGDP成長率は3.3%でOECDの平均2.3%を上回った。上記のほかにも、近隣アラブ諸国との緊張関係を背景に自国のイノベーションを促進せざるをえない事情の元、イスラエルでは失敗を許容する風土と、自由で大胆な発想が許される文化が醸成された。また、イスラエルには男女とも兵役があるのだが、優秀な若者が兵役期間中に軍のインテリジェンス・ユニットに配属されることで先端技術を学ぶ機会を与えられることや、軍事技術の民間転用が推奨され、ビジネスに活用され易いなどの特殊な要因もある。本講演ではこの小さな技術大国であるイスラエルを取り囲む各種の条件を解説し、イスラエルの「イノベーション・エコシステム」を分析し、日本への適用可能性を考え提案する。軍隊を持たない日本に、例えば軍隊のインテリジェンス教育を1つの柱としているイスラエルのエコシステムのスキームをそのまま持ち込むことはもちろんできない。イスラエルのイノベーション・エコシステムから日本でも活用できる要素を分析し、提案したい。
目次:1.初めに、2.イスラエルの歴史、3.イスラエルの経済、4.イスラエルの産業構造、5.イスラエルのエコシステム(1.米国シリコンバレーのエコシステム、2.イスラエルのエコシステム、3.日本とイスラエルの比較)、6.ディスカッション、7.結論
——————————————————————————————————————–
第2報告:「ニューノーマルを見据えた デジタルトランスフォーメーション」(11:00~12:00)
講師:村上 健志氏(日本マイクロソフト株式会社 グループコントローラー)
<プロフィール>2011年、日本マイクロソフト株式会社に入社。国内、および米国マイクロソフト本社にてファイナンス部門、日本マイクロソフトの社長補佐を経験し、2020年10月より現職。マイクロソフト入社以前は、シティバンク N.A、大和証券、 Dell で、主に経営企画、ファイナンス部門を経験。2021年から英国NPO法人FP&A Trends Groupの AI/ML Committeeの役員会メンバーとして参画。国内外の企業向けに、Financeや経営企画部門における機械学習やAI活用、DX事例やデータ活用の講演を実施。
<講演内容の概要>コロナ禍の中、さまざまな業界でビジネスモデルの刷新としてDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速している。アフターコロナを見据え、企業がいかに機械学習やAIといったテクノロジーを活用し、データを使った効果的・効率的な意思決定、データドリブンの経営にシフトしているか。デジタルトレンドとDXの真のメリットとは何か。マイクロソフトの社内事例を紹介しながら、企業が抱える課題と対策について考えたい。講演者が現在所属している、Finance部門、経営企画/管理、財務、経理部門等、データを扱う部門が求められるスキル、資質の変化についても触れたい。
目次:1.ITの急激な進化がもたらす「経営環境の変化」、2.ニューノーマルを見据えたDXの実現に向けて、3.ファイナンス・経営管理部門における課題と対策。a.データを可視化する b.データで意思決定する c.データから予測する d. 議論を活性化させる。4.Key Message: まとめ
———————————————————————————————————————
◆上記の講演と質疑応答の後、講演者を囲んで、若干の交流会を行います(参加自由)(12:00~12:30)
第65回文化観光研究部会(5月11日=オンライン)のお知らせ
第65回文化観光研究部会(オンライン部会=ZOOMを使用)
5/11 「文化観光研究部会」は、株式会社エピテックの藤川様に登場いただきます。
大学生の頃から地方創生活動に携わり、総務省の「地域力創造アドバ イザー」や観光庁の「広域周遊観光ルート専門家」でもある藤川さん。
これからの観光は、マーケティング戦略を行い、ファンをつけることが カギになると考えておられ、地域資源を活かしたコンテンツを地域住民 と考案し、ファンを集めるコミュニティづくりを進めておられます。相模女子大学で、これらをテーマに教鞭もとっておられます。
全国の耕作放棄地を活用した「ご当地バレーボール大会」や、地方創 生活動の大学生によるインタビュー企画「Social Design Girls 17」のプロ デュースなどユニークな活動実績もあり、お話を聞くのが楽しみです!
日時:2021年5月11日 (火)
19:00〜19:45 藤川さんの話
19:45 カンパイ
19:45〜20:05 各地の観光の定点観測
(オーストラリア、知床、京都府の予定) 20:05〜21:00 意見交換
ゲスト:藤川 遼介 様 株式会社エピテック 代表取締役 社長
(MBA・一橋 / 地域アクターズプロデューサー)
https://apitec.jp/
テーマ:ウィズコロナ・ポストコロナの観光 ⑥
ファンづくり型地域振興から考える観光産業
〜観光復興のカギを握る地域住民の笑顔の生み出し方~
参加費:500円 (主催者会員は無料・学生は無料)
主催:関西ベンチャー学会 文化観光研究部会
NPO法人 スマート観光推進機構
協力:なにわ名物開発研究会
申込:https://kanko43.peatix.com
連絡先:星乃 mail:hoshino3014@gmail.com (090-5645-1710)
※ お申し込みの皆さんに、Zoom招待メールをお送りいたします。
講演会(2020年11月13日)開催内容のご報告
講演会(2020年11月13日)開催内容のご報告
2020年度の第2回目となる講演会(全体例会)は、日本IBM株式会社の三輪直人さんを講師にお迎えしました。三輪さんは「日本社会、関西におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進について」をテーマに、①そもそもDXとは②日本のDXの実態③DXを推進するチームの働き方――の3点にについて講演されました。所々で聴講者同士がDXへの取り組み状況などについて話し合う「体感型セッションタイム」をはさむなど、ユニークな講演でした。講演の後の質疑応答では、講師と聴講者との間に活発なやり取りがありました。以下、ご報告です。
テーマ:日本社会、関西におけるDX推進について ~周回遅れを取り戻す~
日時 2020年11月13日(金)18:30~20:00
場所 大阪産業創造館 6階 会議室A・B
講師 三輪 直人 日本IBM株式会社 グローバル・テクノロジー・サービス事業本部
テクニカルセールス事業部 部長 営業統括マネージャー
講師ご略歴 神戸市出身。情報工学修士。2007年、NTT西日本に入社。R&DにてIP電話システム開発の傍ら論文執筆や特許取得を経験。その後クラウドベンチャーへ出向しクラウドエンジニアとしてサービス企画から開発・保守までを経験。2018年より現職。
講演要旨:
日本は人口が減少に転じ、社会の構成が大きく変わっている。ビジネスも大変革期に入っている。個人の個性を重視し、一人ひとりに見合った付加価値のついたモノをつくっていかなければならない時代だ。人口増加を前提とした「前へならへ」型の生産性向上ではなく、ITを活用した「ONLY ONE」型の生産性向上を目指さなければならない。
日本企業の国際競争力は著しく低下した。かつては世界の時価総額ランキングで上位を独占していた日本企業は、現在、ベストテンにも全く入っていない。人口が減少する中で、どうグローバルで戦っていくかが課題だ。いま世界の中心にいる企業は、大量のコンテンツとユーザーをデジタル技術を活用する ことで結びつけるビジネスモデルを確立している。変化の激しいユーザーの要求にタイムリーに応える開発スピードが求められる。ビジネスプロセスをデジタル化する「デジタイゼーション」ではなく、ビジネスモデルそのものを変革する「デジタライゼーション」が必要である。DXとはその「デジタライゼーション」が社会全体に広がっていくことだ。
ことで結びつけるビジネスモデルを確立している。変化の激しいユーザーの要求にタイムリーに応える開発スピードが求められる。ビジネスプロセスをデジタル化する「デジタイゼーション」ではなく、ビジネスモデルそのものを変革する「デジタライゼーション」が必要である。DXとはその「デジタライゼーション」が社会全体に広がっていくことだ。
日本でも例えば、データを活用して安全・安心なクルマ社会を実現しようとする動き、航空会社の乗務員や整備士などの記録を電子化する動き、精神科医療の高位平準化を図る動きなど、DXを進める動きが見られる。自動運転もレベル3まで解禁になった。しかし、うまくいっていない例も多い。変革を起こしたいがITを活用したビジョンが描けない経営者や、外部ベンダーと勝手に新規ビジネスを立ち上げるが変革には至らない事業部門からのプレッシャーがIT部門に集中している。
日本ではIT人材の72%がベンダー企業に、28%がユーザー企業に属しているのに対し、米国では逆に35%がベンダー企業、65%がユーザー企業に属している。欧米のソフトウエア開発は内製が多く、日本のソフト開発は外注が多い。これが日本と欧米の違いである。このため、日本政府も動き出した。例えば経済産業省が進める「DX格付」。先進的なDX企業を育て、国内外から人材や投資が集まりやすい環境をつくるのが狙いである。
DXを支えるインフラは進化している。流れは既存システムからクラウドの活用に進んでいる。クラウドの活用が進むと、家でも仕事ができるようになる。リモートワークへのシフト。これは元に戻せない流れだ。場所に関係なく仕事ができる、時間も調整しやすい、参加者間の力関係が現れにくいなど、リモートワークによるコラボレーションには多くのメリットがある。今後は日本でもシステム開発や運用など、多くの業務がリモートワークにシフトしていくだろう。ビデオ会議や、ファイル共有、チャットなどのツールを活用し、生産性を最大化したい。ただし、ネットワークとセキュリティーの強化も忘れてはならない。
リモートワーク文化をうまく進める上でのテクニックと注意点は、以下の通りだ。①心理的安全性の確保②ビジョンやゴールを伝える機会を増やす③報告フォーマットを決め、成果を見える化する④コミュニケーションの活性化が起きる仕組みを導入する⑤相手の環境を思いやる⑥意図的に休憩時間をつくる――である。まずは経営層・マネジメント層がDXとITに関して勉強することが 大事。そして業務プロセスの中でデジタイゼーションできそうな箇所から探してみることだ。人選して実施してみると社員の意識が変わってくる。
まず、社内でDXを推進できそうな20歳~40歳代の人材を発掘する。その人々に期待している旨を伝えて、プロジェクトをつくる。そして、今の会社・組織の在るべき姿と変革の実行可能性をプロジェクトにレポートしてもらい、小規模でいいのでプロジェクトを実行する。こうした手順を踏みたい。プロジェクトの取り組みを経営層自らが見える化して、推進状況を全体に報告し続ける。実績ができたらプロジェクトチームを評価し社外に発信していく。こうしたことも経営層に望みたい。
以上です
理事選挙結果について
令和3年3月14日
理事選挙結果について
関西ベンチャー学会選挙管理委員長
福嶋 幸太郎
3月14日に開催されました理事選挙におきまして、下記の方が当選されましたので
ここにお知らせいたします。
尚、4月からの学会役職につきましては、決定次第お知らせいたしますので
どうぞよろしくお願い申し上げます。
おかけさまで選挙も無事に終了することができました。皆様のご協力ありがとうございました。
理事当選者一覧
| 氏名 | 所属 | 現学会役職 |
|---|---|---|
| 定藤繁樹 | 関西学院大学名誉教授、大阪学院大学経営学部教授 | 会長 |
| AI農業経営プロジェクト研究部会主査 | ||
| 淺野禎彦 | 淺野会計税務事務所代表 | 副会長 |
| AI農業経営プロジェクト研究部会副主査 | ||
| 小西一彦 | 兵庫県立大学名誉教授 | 常任理事 |
| ビジネスモデルとベンチャー研究部会主査、学会誌編集委員長 | ||
| 松村敦子 | ㈲アクティア代表取締役 | 常任理事 |
| 女性起業家研究部会幹事 | ||
| 文能照之 | 近畿大学経営学部キャリア・マネジメント学科教授、近畿大学経営イノベーション研究所 所長 | 副会長 |
| 地域創造研究部会主査 | ||
| 福嶋幸太郎 | 芸術文化観光専門職大学 | 常任理事 |
| 林茂樹 | 大阪工業大学知的財産学部学部長、特任教授 | 常任理事 |
| 知的財産研究部会主査 | ||
| 大野長八 | 大野アソシエーツ代表 | 常任理事 |
| 地域創造研究部会主査 | ||
| 釣島平三郎 | 太成学院大学経営学部教授 | 常任理事 |
| 畑中艶子 | 国際ファッション専門職大学准教授・立命館大学OIC総合研究機構客員研究員 | 常任理事 |
| 横田英俊 | 大阪ガス㈱ 監査部課長 | 常任理事 |
| 会計 | ||
| 岡崎利美 | 追手門学院大学・准教授 | 常任理事 |
| 女性起業家研究部会幹事 | ||
| 河野万里子 | ㈱色彩舎代表取締役、四天王寺大学非常勤講師 | 理事 |
| 木谷哲夫 | 京都大学産官学連携本部IMS起業・教育部IMS起業・教育部長、特定教授 | - |
| 木本圭一 | 関西学院大学国際学部 教授 | 理事 |
| 深見環 | 四天王寺大学国際キャリア学科教授 | 常任理事 |
| 中部経済研究部会主事、九州研究部会幹事 |
2021年度第1回地域創造研究部会開催のお知らせ
この度,ビジネスモデルとベンチャー研究部会,並びに女性起業家研究部会の協賛を得て,下記のとおり研究部会を開催することになりましたので,ご案内します。多くの方のご参加をお待ちしています。
1.日時:令和3年4月10 日(土)午前10時00分~11時30分
2.場所:ZOOMにて(詳細は,参加申し込みの方に別途ご連絡します)
3.テーマ:「(仮)自分に合った働き方としての起業-女性の自立に向けて-」
4.講師:株式会社アメージング・フューチャー
代表取締役社長 大田原 裕美 氏
<ご経歴>
・国際基督教大学を卒業後,(株)ベンチャー・リンクに入社。
・米国で大流行だったカーブスの存在を知り渡米。日本での展開権利を交渉し取得。日本でのカーブス本部の設立に貢献する。
<株式会社アメージング・フューチャー 概要><<詳細はこちらへ>>
設立 2007年1月24日、自らCurvesのフラインチャイズに加盟し事業拡大。現在、14店舗を経営。
従業員数 50名(2019年10月現在)
事業内容
・カーブス(女性専用フィットネスクラブ)の運営
・フィットネスインストラクターの養成及び派遣
・クラブ運営に関するコンサルティング
5.費用:会員―無料
6.定員:20名
7.問合せ・参加申込先
参加希望者は,氏名,所属,メールアドレスを明記の上,下記までお申し込みください。
お申し込みのあった方に,講演会開催の2日前までZOOM URLをお知らせする予定です。
関西ベンチャー学会地域創造研究部会 主査:文能照之,副主査:大野長八
同 ビジネスモデルとベンチャー研究部会 小西一彦
同 女性起業家研究部会 松村敦子
第64回文化観光研究部会(3月23日=オンライン)のお知らせ
第64回文化観光研究部会(オンライン部会=ZOOMを使用)
オンラインツアーも増えていますが、ツアーの醍醐味はリアルに現地を訪ねることです。それもとっておきのネタを持つガイドさんの案内があると、十二分に満喫できます。
今回は、8年前からガイドブックに載っていない、オモロい大阪を案内されている「プロガイドのたけちゃん」に登場していただきます。
ツアー回数は500回超、人気は「大阪駅びっくりへーほーツアー」です。「大阪駅?」と侮るなかれ、「知らなかった大阪駅」が満載です。
昨年6月から、ネットラジオvoicyにも「たけちゃんの大阪へーほーch」が登場しました。アーカイブは350本。これからツアーと連動されるとお聞きしています。これからも、さらに進化するという「たけちゃんの大阪へーほー話」を、とことんお聞きしてみたいと思います。
日 時:2021年3月23日 (火)
19:00〜19:45 たけちゃんの話
19:45 カンパイ
19:45〜20:05 各地の観光の現状
19:30〜21:00 意見交換
ゲスト:奥村武資(たけちゃん)
『たけちゃんの大阪へーほーツアー~おおさか散歩』
https://www.facebook.com/osakasanpo
https://voicy.jp/channel/1177
テーマ:ウィズコロナ・ポストコロナの観光 ⑤
〜進化するたけちゃんの大阪へーほーツアー~
参加費:500円 (主催者会員は無料です)
主 催:関西ベンチャー学会 文化観光研究部会
NPO法人 スマート観光推進機構
協 力:なにわ名物開発研究会
申込み:https://kanko42.peatix.com
※ お申し込みの皆さんに、Zoom招待メールをお送りいたします。
連絡先:星乃 mail:hoshino3014@gmail.com (090-5645-1710)
第6回ビジネスモデルとベンチャー研究部会
「第6回ビジネスモデルとベンチャー研究部会」
第6回ビジネスモデルとベンチャー研究部会開催のご案内
日時:2021年3月13日(土)10:00~12:30
場所:オンライン(ZOOM)で行います。
参加申込:(参加費は無料)
メールで下記をご記入の上、お申し込みください。3月10日~12日に、
ご記入頂いたメールアドレス宛にZOOM会場に入場用のURL,ID/PWを
お送りします。
メールの件名は「第6回ビジネスモデルとベンチャー研究部会参加」でお願いします。
1.お名前:()、2.ご所属名:()、3.メールアドレス:()、4.電話番号:()
宛先(受付)konishikazu@gmail.com(部会主査:小西一彦)
——————————————————————————–
第1報告:「スマホとSNS によって変化した写真概念」
大平哲男氏(阪神写真館代表取締役社長、大阪商業大学非常勤講師)
<プロフィール>
1957年 神戸市生まれ。青山学院大学経営学部卒業。神戸商科大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学。ミノルタカメラ株式会社を経て株式会社阪神カメラ入社。現在、阪神写真館株式会社代表取締役社長。
*論文「日米フイルム摩擦の顛末―コダックによる301条提訴と富士の対応」『貿易と関税』第46巻第4号,平成10年4月(財)日本関税協会、他。
<講演内容の概要>
私がカメラ業界に初めて入った当時は、多くのカメラ店はDPE事業からの収益に依存していた。次第にデジタルカメラが主流になることによって、多くのカメラ店は廃業していった。そのような中において、弊社は写真館へと転換して会社の存続を図った。しかし、その写真館の多くもカメラ店ほどではないにしろ衰退している。 そして「写真」の概念も、撮影機器(カメラ)の進化にともない変化した。デジタルカメラの登場前は、私たちはプリントにされたものを「写真」と呼んでいた。それが、画像に変わり、加工されたものになった。最近は「スマホ」で「写真」を撮るようになっている。「カメラ」は「スマホ」であると言って過言でないかもしれない。
「スマホ」の登場で、「写真」の概念は、ハード面から変化しただけでなく、ソフトやサービスの面からも変化している。その利便性の高さが写真の撮影でも評価され、撮影の仕方や「写真」に対する考え方、関連のビジネスまで変化している。とくに「SNS」との親和性の高さのインパクトは大きい。「スマホ」と「SNS」の組み合せで、これまでの写真の顧客層は拡大したが、これまで顧客層でなかった人々(女性層)も顧客層に加わっている。このように、「写真」の概念は時代とともに変化し、写真ビジネスも変化し、新しい写真文化が生まれている。
——————————————————————————————————-
第2報告:「中古ブランド品販売企業における鑑定士育成システム」
安藤 根八氏(あんどうこんぱち)(大阪市立大学大学院創造都市研究科博士課程)
<プロフィール>
大学卒業以来45年間、流通、廃棄物、環境、リサイクル、リユースの編集、出版事業に従事し、新聞メディアやNHK情報番組「生活ほっとモーニング」にコメンテーターとして100回以上情報を提供した。しかし、中古品流通の学術的価値を論じた文献はまだ存在していないことに気づき、2016年、68歳で大阪市立大学大学院創造都市研究科修士課程に入学。2018年に同大学院博士課程国際地域経済領域に進学して、中古品流通の研究を進めている。
<講演内容の概要>
中古ブランド品販売企業にとって競争優位を確保するためには、優秀な鑑定士を育成し、買取り商品の増大を目指すことが必要である。豊富な商品知識と真贋鑑別能力を有し、買取り価格の査定を行う鑑定士は熟練人材であり、経営資源である。「中古ブランド品業界トップ」「質屋業界トップ」「買取に特化するベンチャー企業」を特徴とする業界大手3社の鑑定士育成について、野中郁次郎の「知識創造理論」の4つの知識変換プロセス「SECIモデル」を分析フレームとして、「暗黙知」から「形式知」へとスパイラル変換していく過程を3社のビジネスモデルに沿って明らかにする。